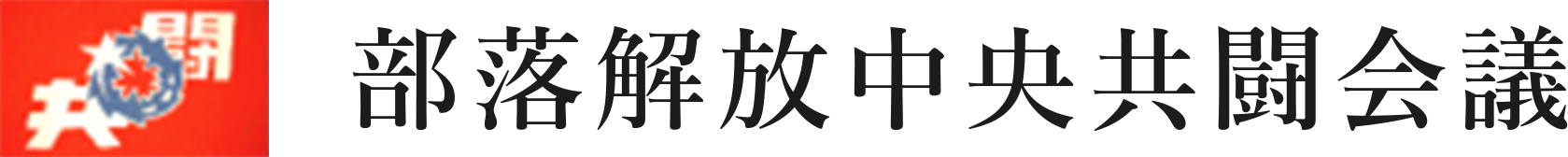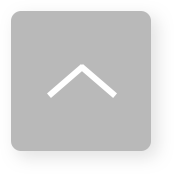WORKS
私たちの活動
部落解放・人権政策確立運動、「人権侵害救済法」の制定に向けての活動
人権侵害救済法の制定は、あらゆる人権侵害に対して迅速かつ効果的な救済を提供するための重要な一歩です。
この法律の制定により、差別や人権侵害を未然に防ぎ、被害者が適切な保護を受けられる社会を構築することを目指しています。
私たちはこの法案の実現に向けて、社会全体への理解促進と支持拡大を図るための活動を続けてまいります。
「世界人権宣言」具体化のとりくみ
私たちは、「世界人権宣言」の理念を具体化し、日常生活の中で実践される社会を目指して取り組んでいます。
「世界人権宣言」は、すべての人々が平等に尊厳と権利を享受するべきであるという共通の価値観を示しています。
私たちの活動は、この宣言の理念を具体的な行動や政策に反映させることで、差別や不平等をなくし、すべての人が尊重される社会の実現を推進することにあります。
就職差別と職場のあらゆる差別撤廃のとりくみ
就職の際に生じるあらゆる差別をなくし、すべての人が平等な機会を享受できる社会を目指しています。
履歴書の情報や出身地、性別、年齢などが就職活動において不当な判断材料とされることなく、個々の能力や適性が公平に評価される環境づくりを推進しています。
この取り組みを通じて、就職の平等と人権の尊重が守られる社会を実現してまいります。
「人権教育・啓発推進法」の活用など、人権教育・啓発活動
人権の尊重はすべての社会の基盤です。
私たちは、学校や地域社会における人権教育の推進を支援するとともに、企業や団体と協力し、職場での人権啓発活動を展開しています。
講習会やワークショップを通じて、差別や偏見をなくし、すべての人が安心して生活できる社会の実現に向けた取り組みを続けています。
狭山事件の再審要求
狭山事件は、冤罪の可能性が指摘され続けている事件であり、司法の公正さと人権の尊重が問われています。
私たちは、この事件の真相を明らかにし、被害者とされた方の権利が適切に守られるために再審を強く要求しています。
公正な裁判の再実施を通じて、正義を実現し、同様の不正が繰り返されない社会を目指します。
用語解説
-
差別糾弾闘争
差別糾弾は、差別をした人に対し抗議するという側面を持っていますが、決して報復的なものではありません。差別を受けた人の人間としての生きる権利の主張ともいえます。
また、差別の非人間性や差別社会の問題点を明らかにし、差別をした人が自分の課題として差別撤廃に取り組む自覚を持つ人間に変わることを目指しています。
当初、差別意識は、遅れた意識をもつ個人の問題だととらえられていましたが、運動の発展にともない、社会構造や現実の社会の実態を反映した社会意識としてとらえられるようになりました。この考え方によって差別糾弾闘争は、差別行政糾弾闘争と結びつけて推進されていきます。 -
差別行政糾弾闘争
被差別部落の劣悪な生活や住環境の実態が差別を再生産しており、それを放置し温存してきた行政は差別行政であるとして、行政に差別的生活実態を改善させるよう迫る運動です。1950年代から自治体に対する闘いとして広がり、国策樹立運動と平行して発展し、「同和問題の解決は国の責務であり、国民的な課題である」ことをうたった「同和対策審議会」答申(1965年)と「特別措置法」の制定に結びつきました。
-
「部落解放基本法」制定運動
部落差別を解消するための法としては、長年の運動の成果として1969年に「同和対策特別措置法」が10年の時限立法として制定され、以後、事業縮小をともないながら「延長」されてきました。
しかし、これまでの法が環境改善などハード面の事業を中心としたものだったため、環境面について一定の改善をみましたが、教育、啓発、就労などソフト面の対策が遅れ、総合的な施策を可能とする法の必要性が叫ばれました。また、差別を商う行為や就職差別については法律で規制する必要もあり、これらを総合して「部落解放基本法」を要求する運動が高まりました。
その成果として、これまでの事業法については、対象事業も絞り込まれましたが5年の期限で延長となりました。一方昨年12月、運動の成果として「人権擁護施策推進法」が制定されました。今後の課題は、「人権擁護施策推進法」に基づき審議会が設置され、「教育・啓発」と「人権侵害救済」の法制定について検討がなされるので、実効ある法律が制定されるよう働きかけていく必要があります。 -
狭山差別裁判糾弾闘争
狭山事件とは、1963年5月1日、埼玉県狭山市で女子高校生が行方不明になり、殺された事件です。警察は40人もの警察官を張り込ませながら、身代金を取りに現れた犯人を取り逃がしました。当時、吉展ちゃん事件の犯人も取り逃がしており相次ぐ大失態を演じた警察は、世論の大きな非難を浴びました。捜査に行き詰まった警察は、付近の被差別部落に集中的な見込み捜査を行い、石川一雄さん(当時24歳)を別件逮捕し、1ヶ月にわたり警察の留置所で取り調べ、ウソの自白をさせ、犯人にでっち上げたのです。
今日までに、石川さんの「自白」がでっち上げであることが、多くの証拠によって明らかにされています。
また、被差別部落住民に対する予断と偏見にもとづいて集中的な捜査がなされ、判決の内容までもそのことが反映していることから、私たちはこの裁判を狭山差別裁判として糾弾し、公正な裁判を要求しています。 -
「部落地名総鑑」差別事件
この事件は1975年に発覚したもので、『人事極秘・特殊部落地名総鑑』がダイレクトメールを使って販売されていることが明らかになりました。この書籍は、全国の被差別部落の所在地を新旧地名で示し、主な職業や世帯数などを記載し、一冊3万円程度で売られていました。ダイレクトメールの内容は、採用において被差別部落出身者を排除することをそそのかすものとなっており、また書籍の内容もその目的にしか使えないものでした。この書籍を購入したのは、わかっただけで一部・二部上場企業を中心に二百数十社におよび、部落解放同盟は組織をあげて糾弾闘争に取り組みました。この事件の反省を契機に企業での「同和研修」が広く行われるようになりました。また国や自治体なども採用差別を防ぐ啓発も前進しました。
-
統一応募用紙
就職に際して、本人の能力や適正・人格とは全くの関係ないことを応募用紙に書かせたり、面接で聞いたりすることがあります。そのなかで、例えば次のような内容は就職差別につながります。「本籍地」「家族関係・家族の職業や収入や学歴」「支持政党や尊敬する人物」「宗教」「既婚・未婚」「住環境」
部落解放運動によってこうした点が指摘され、差別・排除を目的とした不適切な項目を除いた「全国高等学校統一用紙」(統一応募用紙)が1973年に作成され、労働省・文部省から行政指導されるようになりました。一般用(JIS規格)や大卒予定者用参考例などにも同様の主旨が行政指導されるようになりました。 -
人権教育のための国連10年
1994年12月の国連総会で、1995年から2004年までを「人権教育のための国連10年」とすることが決まりました。これは、世界人権宣言が採択されてから40年を経て、その具体化に向けて多くの人権条約が採択されましたが、その周知徹底と具体化が強く求められており、とくに冷戦終焉後の民族や宗教による紛争や差別の多発という深刻な状況を踏まえ、平和な国際社会をつくるために、世界的に人権文化を創造する必要があり、人権教育を飛躍的に強化しようとするものです。
そして国連は、各国政府に人権教育センターの創設、人権教育計画の構築などを目標にした行動計画を策定することなどを呼びかけ、国連高等弁務官に報告することなどが義務付けられています。
人権教育の対象とされているのは、子どもだけではなく、大人、それも警察官や裁判官、国会議員や官僚が重要な対象となっています。また、教育、行政現場はもちろん、地域、家庭、企業など社会のあらゆる人々によって人権尊重が語られる状況をつくることが呼びかけられています。その意味で、民間団体の活動も重要です。
国連では、「人権教育とは、知識と行動力を分かち伝え、態度を育むことを通して、人権の普遍的な文化を形成しようとする教育、訓練、情報提供の取り組みと定義することができる」と明らかにしています。
日本においては、1997年7月に政府の行動計画が発表されましたが、その後の目新しい施策や予算措置もほとんど無い現状があり、働きかけが必要となっています。運動の成果もあり、自治体においても19府県(99年末)で行動計画が策定されました。 -
エセ同和
「エセ同和」行為は、社会に存在する「部落は怖い」「何をするかわからない」などといった差別意識や偏見を悪用し、利権をあさり、私腹を肥やそうとする行為で、装いがいかなるものであっても、部落解放運動とは無縁のものです。かえって、差別意識を助長するものです。
部落差別の撤廃をめざす団体としては、全国水平社のからの伝統を引き継ぐ部落解放同盟があり、「部落解放基本法」制定運動や就職差別禁止の法整備、人権教育の推進などの運動に取り組んでおり、労働組合や宗教者、市民、行政、企業、などが連携して取り組みを進めています。この部落解放同盟もこの「エセ同和」行為を厳しく批判しています。
「エセ同和」行為は、「同和××連合会」「部落××協会」などを名乗り、中には部落解放同盟を詐称して高価な書籍を押し売りしたり、金品を強要するものです。このような行為が増えたのは、1981年の「商法改正」によって締め出された「総会屋」や暴力団などが、企業などに食いつき、利権をあさるため「同和問題や人権問題を口実にすれば企業に入り込める」として、「エセ同和」団体に転身したからです。したがって、「エセ同和」団体が押し売りしている高価な書籍も、行政や部落解放同盟の出した資料を勝手に掲載したりしたものがほとんどです。
このような反社会的行為を撲滅するには、毅然たる態度で拒否することが大切です。悪質な場合は法的手段も必要でしょう。そして、何より部落問題に対する正しい理解を広めることが大切です。
また、被害を受けた企業や団体に、「エセ同和」団体につけ込まれるような差別や人権問題がある場合もありますが、問題点は改善し、差別撤廃と人権擁護を進めていく必要があり、部落解放同盟や行政に相談することもできます。